スポンサーリンク
最近、仕事のことでテンション下がりっぱなしだったので、気分転換にと重かった髪を少しカットしました。その時、美容院でたまたま手にした雑誌に、「太鼓持ち」のことが書いてあったんですよね。
「太鼓持ち」って、どちらかと言えばこんなイメージではないでしょうか?
媚びを売って要領よく立ち回っても、相手に見透かされたら逆に失敗して大けがをするわ! なんて思った私は、読み流そうとしたんです。
ところが、読み進めてみると・・・それはとんでもない!太鼓持ちこそ、仕事も人間関係も上手くいく愛されキャラなんだとか。下がったテンションもアップさせる人間関係の達人技だったのです。
誰しも褒められると悪い気はしませんよね。相手も喜び、自分も気に入られる「WINーWIN」な関係。
そんな太鼓持ち、実は賢くなければ務まらない職業だったそうなんです。今回は、その 語源 や スキルの磨き方 など、私が興味をそそられた内容をご紹介したいと思います。
そんなん必要ないわ!という人もちょっと見ていかれませんか?普段の会話にさりげなくプラスするだけで、相手の心をグッと掴めそうなフレーズもありますよ!
太鼓持ちの語源

そもそも「太鼓持ち」とはどういう人のことをいうのでしょう? その語源に迫ってみます。
歴史は古く、豊臣秀吉のお話相手「御伽衆(おとぎしゅう)」であった曽呂利新左エ門という人物が始まりです。この人がとてもウイットに富んだ武士で、「太閤、いかがで。太閤、いかがで。」といつもご機嫌を伺い持ち上げていたそうです。そうして「太閤持ち」 から「太鼓持ち」 になったと言われています。
そしてその後、お座敷で踊りやお囃子で宴席を盛り上げる男芸者のことをいい、正式には「幇間(ほうかん、たいこ)」という職業となりました。
間・・・人と人の間、つまり人間関係
幇間は、接待する側とされる側のお客さん同士や、お客さんと芸者の間の雰囲気が途切れないようにしなければなりません。
周りに常に気を配り、場を盛り上げ、上手く立ち回るには、賢くなければ務まらない職業 だったのです。
賢いと言っても、いわゆる勉強ができるということではありません。では、具体的にどういう風なことなのかを少しご説明しますね。
スポンサーリンク
太鼓持ちは理想の愛されキャラ
空気を読むことができる、コミュニケーション能力に長けている人なのです。
私もそうなんですが、褒めることや褒められることに慣れていません。これは日本人特有のようですね。だからこそ、褒め上手 が重宝されるのです。
例えば・・・落語にも調子のよい「幇間(太鼓持ち)」が出て来るお話があります。
京都の旦那とお茶屋のおかみ、芸妓や舞妓とともに愛宕山に登ることになった幇間。
山の上では旦那が谷底の的へ小判を投げ、「これが本当の散財」と遊びに興じていた。
「その投げた小判は拾ってきた人のもん」と言われ、怖いながらも必死で崖を飛び降りて小判を拾い集めた幇間。が、しかし今度は上がることができなくて悩む。
なんとか方法を考えようやく崖から這い上がってきたところ、一生懸命拾った小判を忘れてきてしまった、というお話。
酒でしくじり、仕事を失った幇間の久蔵。
富くじ(現在の宝くじ)をそそのかされて買い、もし当たれば堅気になろうと考えていた。
そんな夜、しくじった旦那の家が火事に。
火事見舞いに駆けつけ、旦那を喜ばせる。
ところが、自分の住んでいた長屋も火事になり、家が焼けてしまう。
後日、神棚に置いていた富くじが当たっていたことを知り、家が焼けたのですでに富くじは無いと悲しんだ。
すると長屋の友人が、布団と釜と神棚を火事場から出してくれていた。
正直者が救われるというお話。
このように、落語の中の太鼓持ちは、一挙手一投足が面白くて憎めない存在なのです。
幇間は基本的に相手に逆らいません。そして何よりタイミングよく相手を笑わせ、楽しい気持ちにさせるのです「IQよりも愛嬌」失敗しても「てへへ」と交わすことで上手くいくものなのです。
これには、私も納得です! 私なんかも勉強のできる方ではないですが、オンナは愛嬌! がモットーですから。
そこで、太鼓持ちに学ぶ、普段の会話にも役立つフレーズを最後にご紹介しますね。
必勝フレーズ「さしすせそ」
 さりげなく口にすることで、相手にピタッとはまり、気持ちをグッと持ち上げることができるフレーズ。それが「さしすせそ」なんです。
さりげなく口にすることで、相手にピタッとはまり、気持ちをグッと持ち上げることができるフレーズ。それが「さしすせそ」なんです。
どんな言葉で、どう使うのか。では、いってみましょう!
- さ・・・「さすが」
「さすが!」とハイテンションで言うのも良し、「さすがですね」としみじみ感心して言うのも良し。使い勝手のいいフレーズです。 - し・・・「知らなかった」
先輩風を吹かせたがる人にはピッタリ。相手の気持ちを持ち上げるキラーフレーズです。 - す・・・「すごい」
シンプルながらパワー絶大の褒め言葉。プライドの高い人には特に効果的なフレーズです。 - せ・・・「センスいい」
相手のこだわりや自信のあることについて褒めるとテンションアップ。広い範囲で使える万能フレーズです。 - そ・・・「そうなんだ」
興味を示す様子で楽しそうに言うことがコツ。好感度アップのご機嫌フレーズです。
「さしすせそ」のフレーズを上手く駆使して相手の気持ちを持ち上げて、楽しい気持ちにさせましょう。気分を害するようなNGワードは、うっかりでも使わないように注意しましょうね!
めざせ!現代のデキる「太鼓持ち」
スポンサーリンク
さいごに
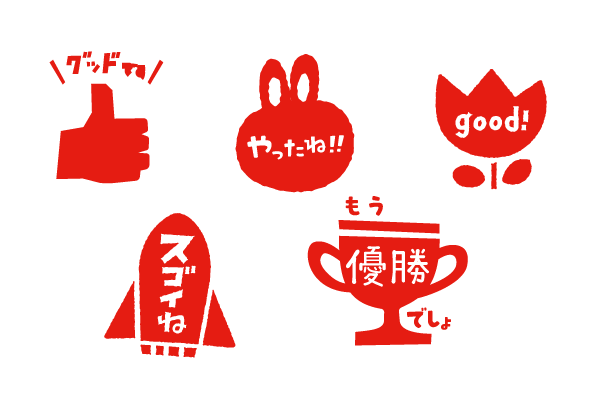
気分転換にと髪を少しカットしに行った美容院で、たまたま目にした「太鼓持ち」のこと。その語源や人間関係を上手くするスキルなど、今の私にはとっても興味をひく内容でした。
そんな「太鼓持ち」についてを今回、私なりにまとめてみました。いかがでしたか?
ご機嫌取りのゴマすり という、どちらかと言えば感じのいいものではなかった「太鼓持ち」のイメージ。その語源の歴史は古く、豊臣秀吉のご機嫌取り「太閤持ち」から「太鼓持ち」となったのです。そして実は、賢くなければ務まらない職業だったのです!
人間関係の達人になるフレーズは 「さしすせそ」
- さ・・・「さすが」
- し・・・「知らなかった」
- す・・・「すごい」
- せ・・・「センスいい」
- そ・・・「そうなんだ」
日本人はとにかく褒められ慣れていないので、褒めるのも下手です。だから、いきなり褒めすぎるのはちょっと・・・という人は、まず、リアクションを笑顔で大きく。そして、少しずつこの「さしすせそ」を実戦していきましょう♪
太鼓持ちというほどのものではないのですが、私は人を気持ちよくさせる会話などは、わりと得意なほうだと思っていたんです。でもここ最近、仕事のことで、ちょっとブルーな日々が続いていました。「自分が変われば相手も変わる」と思ってなんとかやっていましたが。
残念ながら、本当に自尊心の強い人には「太鼓持ち」も通じないこともあります。 そんな時は、あっさりと諦めましょう。私はそう思います。
今回、たまたまとはいえ、「太鼓持ち」について知ることができたのは、私にとってはとてもいいタイミングの「気づき」だったんだと思いました。
恋も仕事も友情も “褒め” 次第。参考になれば幸いです。
スポンサーリンク
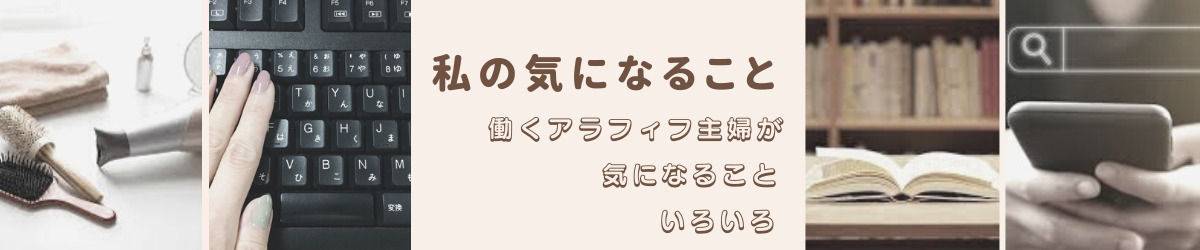
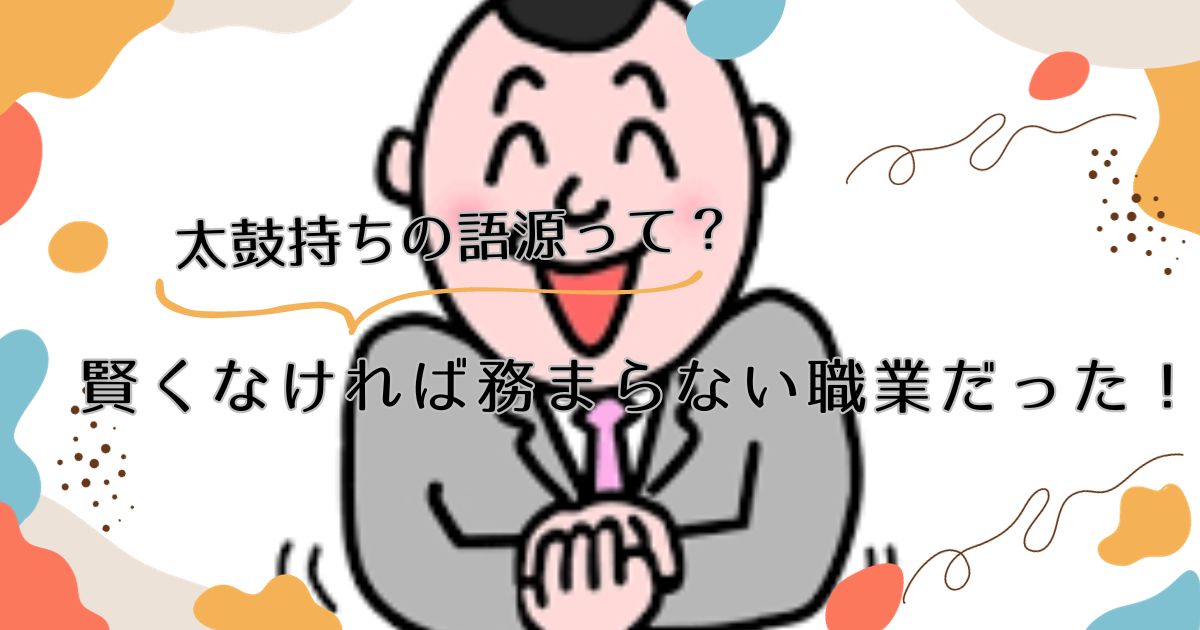
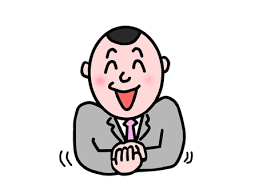



コメント
(^_-)-☆