スポンサーリンク
義父が亡くなりました。それが、1月1日に息を引き取ったのです。悲しみや様々な想いはあれど、それでも送らなければなりません。
一通りのことが一段落したあと、ふと思ったのが喪中についてなのです。

喪中って、こんな場合はいつからいつまでになるんだろう…
喪中というのは、約1年間というのはだいたいは分かっていたのですが・・・

元旦(1月1日)に亡くなった場合はどうなるのだろう?
ふとそんな疑問がわいてきたのです。
そこで今回は1月1日死亡の場合について、いつからいつまでなのか? 喪中の範囲や、その他に気をつけるべきことがあるのか? マナーについてなど、いろいろ気になり調べてみました。
知らないでは済まされない私と同じような立場の方々にも、ぜひ参考にしていただければと思います。
喪に服す期間について
家族や近親者が亡くなったとき、残された遺族は外出を控えたり故人の冥福を祈ったりと、一定の期間身を慎むことを喪に服すといい、大きく分けて、「忌中」 と 「喪中」 の2つがあります。
- 忌中
四十九日法要までの期間 - 喪中
(故人との関係によって変化しますが)およそ一周忌までの期間
奈良時代には「養老律令(ようろうりつりょう)」や江戸時代には「服忌令(ぶっきりょう)」といって、喪に服す期間というのは法律によって明確に決められていました。
現代では、明治時代に定められた「太政官布告(だじょうかんふこく)」という法律が目安とされています。この法律は昭和22年に廃止されていますが、判断基準となっていました。
| 故人との関係 | 喪中期間 |
|---|---|
| 父母・夫 | 13ヶ月 |
| 義父母・祖父母(父方)・夫の父母 | 150日 |
| 妻・子供・兄弟姉妹・祖父母(母方)・伯叔父母・曾祖父母 | 90日 |
| 養子 | 30日 |
ただ、男尊女卑など当時の時代背景もあり、女性に対しての服喪期間が短かったりします。現在ではだいたい以下の表のような期間としているようです。
だたし、これも宗教の違いや個人の気持ちや判断によるものとされ、明確に決まっていないようですが。
| 故人との関係 | 喪中期間 |
|---|---|
| 父母・義父母 | 12ヶ月~13ヶ月 |
| 子供 | 3ヶ月~12ヶ月 |
| 祖父母 | 3ヶ月~6ヶ月 |
| 兄弟姉妹 | 30日~6ヶ月 |
| 伯叔父母・曾祖父母 | 喪中としない |
これらを踏まえてまとめると、現在では
というのが一般的なようです。
そして数え方の基準としては、葬儀を出した月からではなく、亡くなった月から数えます。
二親等とは、本人または配偶者から数えて二世を隔てた関係のある人。
一親等にあたるのは、本人及び配偶者の両親と子供。
二親等は、もうひとつの家系図をすすめたところにいる人達。つまり、祖父母、兄弟姉妹、孫です。
引用元:http://www.kawachisousai.co.jp/contents/if/range/
では、この喪中期間に気をつけることってどんなことでしょうか?
知らずにしていることもあるかもしれないと、ふと気になったので。次にご紹介しておきますね。
スポンサーリンク
服喪期間のマナーについて
今回の私の場合は、1月1日に亡くなったということもあり、お正月に関するマナーについてとても気になったので調べてみました。
門松や、しめ縄、鏡餅などの正月飾りは控えるようにします。
お正月は、豊穣の神様であり、家々に1年の実りと幸せをもたらす歳神様を迎える行事です。そして無事に1年を迎えることができた感謝をし、それを喜ぶ意味もあります。喪中であるということは、近親者が亡くなったという意味では無事に1年を過ごして、新しい1年を迎えることができなかったということになるからです。
忌中は控えるようにします。
神道においては「死」を穢れとされているため、神社へのお参りは忌中(四十九日まで)の間は控えるようにします。仏教の場合は、神道と違い、「死」を穢れとしないため、忌中であってもお参りしてもよいのだそうです。神社も、忌明けの後であれば、お参りしてもよいとされています。
忌中は控えるようにします。
おせち料理についても、歳神様に由来したお祝いの料理とされているので、忌中の間は控えるようにしたほうがよいでしょう。ただし、お祝いの料理としてでなく、あくまでも普通の食事として食べるのなら問題はないようです。
年賀状の交換は辞退するのが一般的です。
1年以内に近親者が亡くなった場合は、喪中・年賀欠礼はがきを出して、年賀状の交換を辞退します。今回の我が家の場合は、1月1日に亡くなったので、来年の年賀状を辞退という形になります。
ご主人と故人との続柄を書きます。
今回の私の場合です。義理の父(主人の実父)が亡くなった場合、喪中はがきには私の名前も連名で書きますよね。私にとっては義父でも、亡くなった人の続柄は主人との関係を記載します。
できれば、もらった相手のかたも分かりやすくなるので、下の名前だけでなくフルネームで書くのがベター。
余談ですが、お正月以外にちょっと気になったのが結婚に関するお祝いごとです。それについても一般的なマナーを少しご紹介しておきますね。
入籍については喪中でも問題はありません。
結婚式はお祝いごととなるため、喪中の間は控えるほうがよいといわれています。挙式の予定がある場合は、延期をするほうが望ましいです。しかし、すでに招待状を出している場合は、式場や出席者の都合もあるので、全てにおいて事情を説明し、手続きができるのであれば、ということになるでしょう。
これも、絶対という決まりではありません。故人が生前に楽しみにしていた場合であるとか、故人の供養のためにもという場合であるとか、様々な事情があると思いますので、ケースバイケースです。
また、結婚式に招待された場合は、一般的には先方に事情を説明した上で、なるべく出席を控える方がよいでしょう。この場合は、忌明けに改めてお祝いの言葉を伝えたり、お祝いを贈ったりしましょう。
この場合も、お付き合いの度合いなどもあると思いますので、親戚に相談するなど常識的な範囲で考えるとよいかと思います。
スポンサーリンク
さいごに
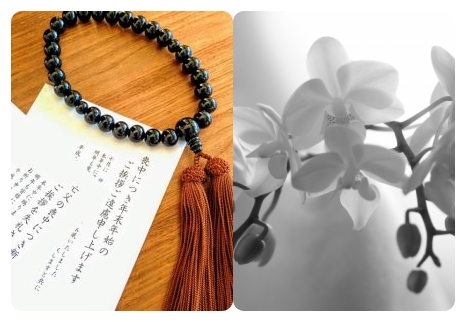
義父が1月1日に亡くなり、葬儀・告別式など一通りのことが済んだあと、ふと気になったのが喪中の期間と範囲。
その他にも気をつけるべきことなど、マナーについて知らなかったわ!なんて他人ごとでは済まされない年齢にもなっているので、リサーチしてみました。
いかがでしたか?
- 四十九日法要までの期間を「忌中」
- およそ一周忌までの期間を「喪中」
大昔から、喪に服する期間は法律で決まっていたようなんですね。
しかし、現在では故人との関係性や気持ちによるところで判断され、総合して一般的には以下のようになっているようです。
かつては、殺生を禁じたり、お酒を飲んだり肉を食べることを控えたりとしていたようですが、現在ではそれほど厳しく身を慎むことはありません。
けれども、私が今回気になったように、お正月というのは「歳神様を迎える」「新年を祝う」 という意味でも、初詣や正月の祝い飾り、祝い膳などは控えるのがマナー。
結局、どういう場合も気持ち次第ということが大きいようですね。
そして、地方のしきたりなども大いに関係してくるので、できれば目上の人に相談して意見を参考にするのが一番だと思います。
【こちらの記事もぜひ参考に♪】
追善供養の意味とは?心なごむ3つのお供えについて
喪中はがきと寒中見舞い!両方出すほうがいいの?!
お歳暮のマナー!喪中の時はポイントを押さえると安心!
喪中はがきはいつ出す?初めてでも慌てないで!
スポンサーリンク
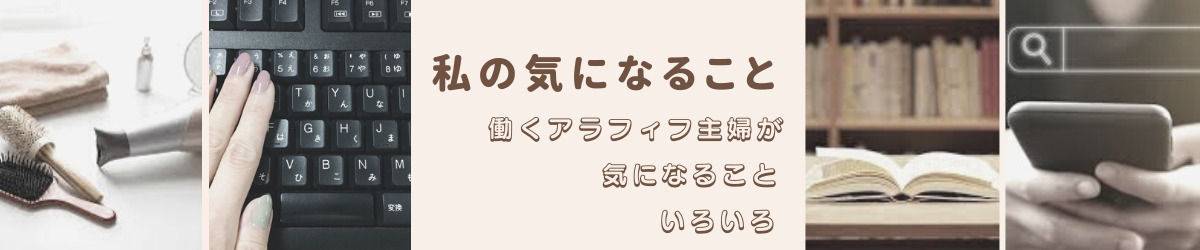
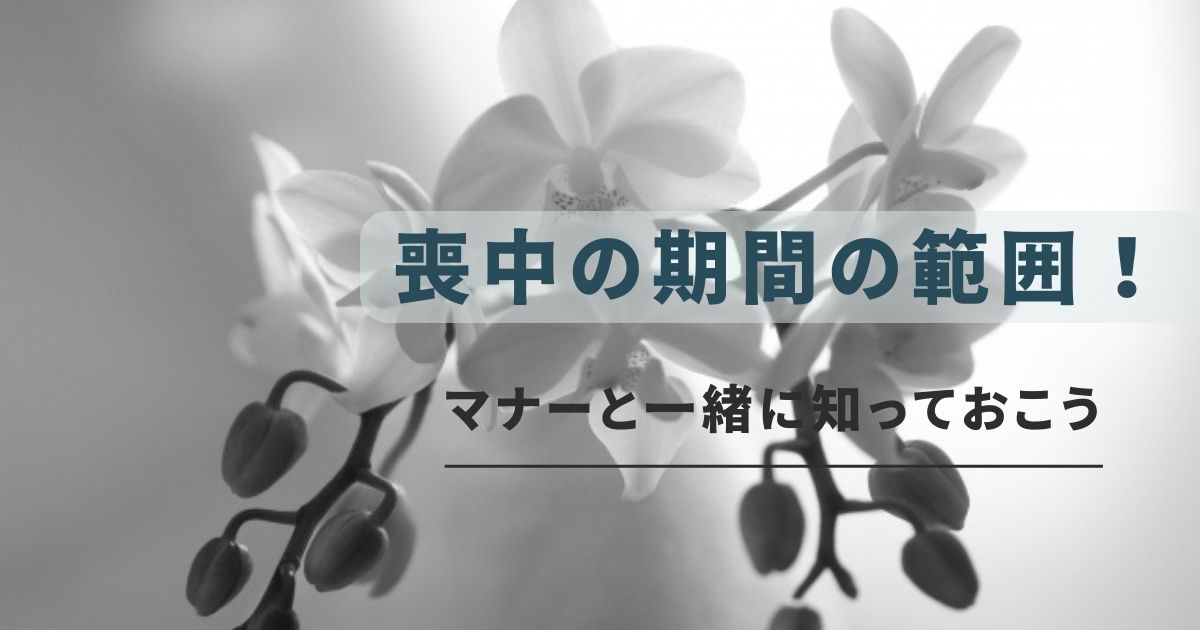

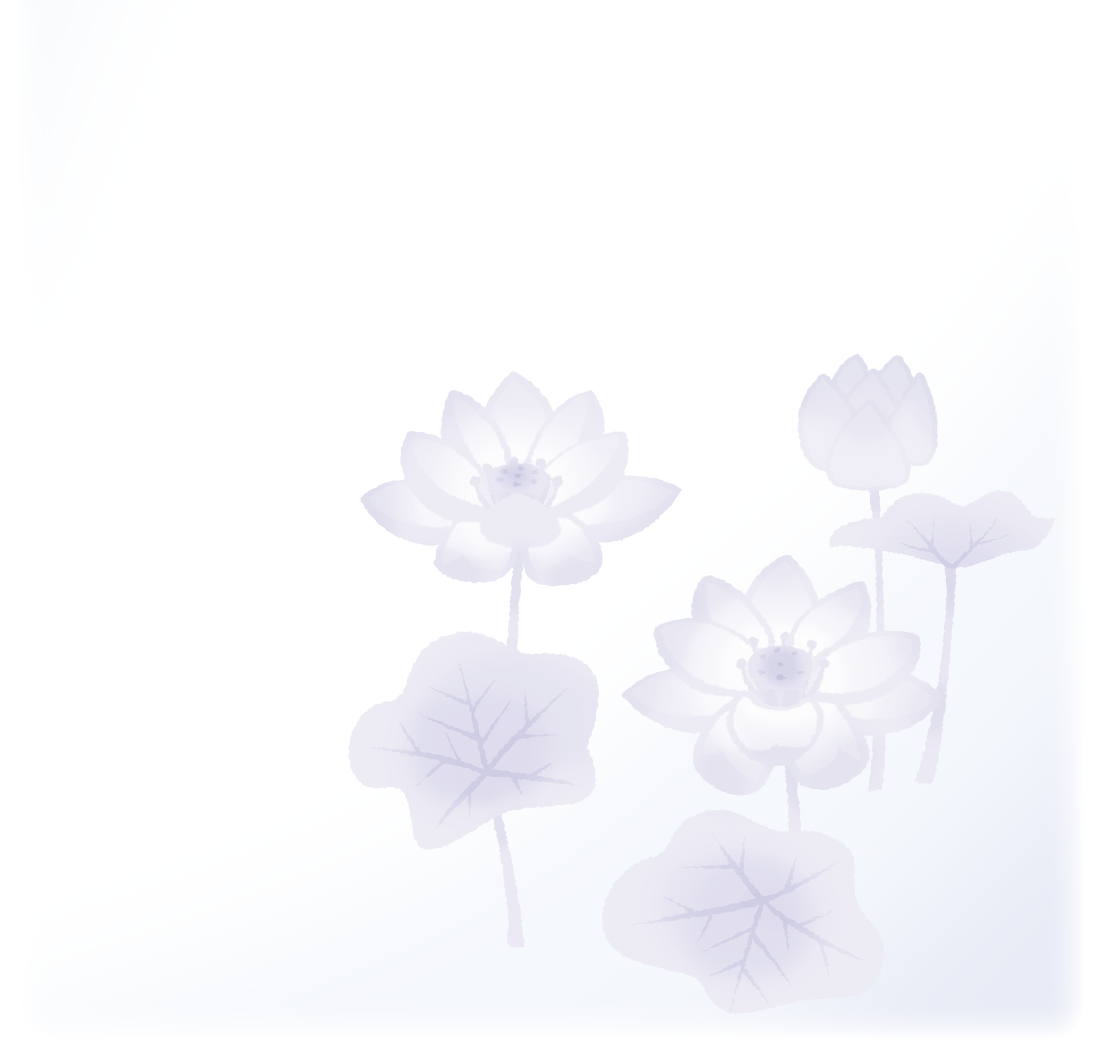

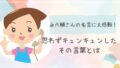

コメント